千代田区の
クラウド会計専門会計事務所
会計事務所タクシスは、
「相談しやすい、親しみやすい」をモットーに、
スモールビジネス の成長を税務・会計面からサポートします。


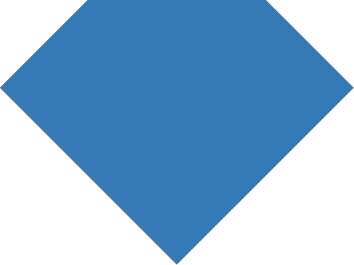
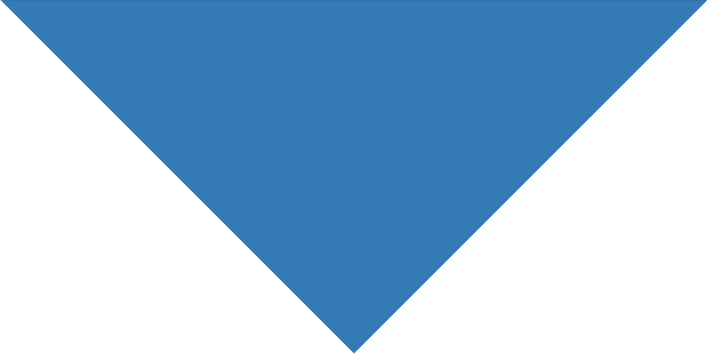
会計事務所タクシスは、
「相談しやすい、親しみやすい」をモットーに、
スモールビジネス の成長を税務・会計面からサポートします。


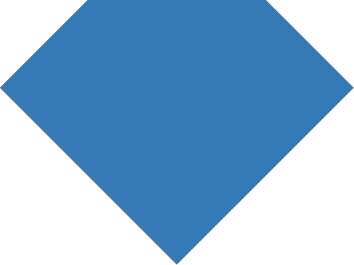
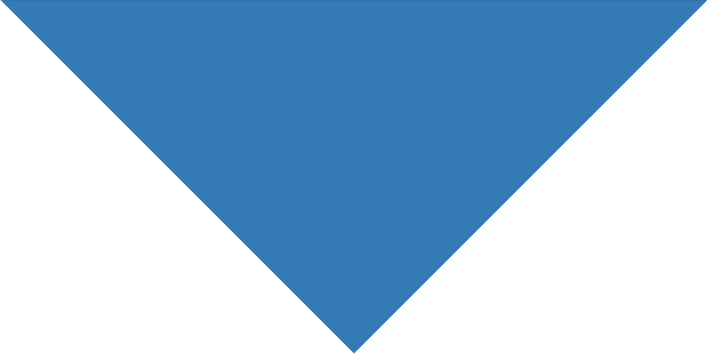
About

「数字に強い」優れた経営感覚を持った経営者を輩出する
エンジニア出身、創業融資、IT・クラウド会計に強い
若手税理士が代表です。
士業というとカタいイメージをお持ちの方がいらっしゃいますが、「相談しやすい、親しみやすい」をモットーとしております。
クラウド会計、融資・資金調達に詳しいことが当事務所の強みです。
クラウド会計ソフト、マネーフォワードクラウド(MFクラウド)/freee/弥生オンライン対応。
中小企業、フリーランス・個人事業などスモールビジネスの成長を
あらゆる面からサポートします!
Tax Accountant

代表税理士
伊藤篤史 ATSUSHI ITO
1982年生まれ。愛知県名古屋市出身、東京都在住。
大学卒業後、SIerに就職。システムエンジニアとしてシステム開発、導入に従事する傍ら、
税務、会計を通じて企業経営に深く関わる仕事をしたいと感じ、税理士を志す。
会計業界に転職後、事業会社の財務経理部門、会計事務所勤務を経験、勤務期間中に税理士試験合格。
2006年
一橋大学社会学部社会学科卒業
2017年
税理士試験官報合格
(簿記論、財務諸表論、法人税法、所得税法、消費税法)
2018年
税理士登録、当事務所開業


service
顧問として寄り添いながら、貴社の事業の成長を会計・税務面からサポートいたします。

サービス内容






service
融資に関する幅広い経験・知見を基に、融資に関する面倒ごとやお悩みを解決いたします。

サービス内容





Advantage
1.経営の相談に乗ってほしい、アドバイス・提案をしてほしい
2.銀行対策、融資の相談がしたい
税理士の業務範囲は、税務書類作成、税務相談などが主となりますが、それだけでは経営者様のニーズに応えられるわけではありません。
当事務所では、経営者様のニーズに応じた各種サービスをご用意しております。
1

クラウド会計ソフトの新規導入、既存ソフトからクラウドへの移行など、数多くの経験、知識を有しております。
・メリット
1.時間、場所、環境を選ばず、会計データの閲覧、更新ができます。
2.リアルタイムに関係者と会計データを共有できます。
3.インストール型のソフトと比較すると、低コストで導入できます。
4.データのバックアップ、ソフトのバージョンアップが不要になります。
5.経理業務に要する時間の削減が期待できます。
2

システムエンジニアとして、システム開発、導入に従事していた経験を持っております。
その経験を活かし、会計まわりのみならず、ITを活用した業務改善の提案など、経営者様の経営課題解決の一助となることができたら幸いでございます。
3

Price List
税務顧問報酬 月額15,000円~
記帳代行報酬 月額10,000円~
決算申告報酬 60,000円~
※法人、設立初年度・記帳代行無し(自社で会計入力)の場合
月額15,000円、決算申告報酬60,000円 年間合計240,000円
| 調達金額 | 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 30,000円 | 調達金額の2.5%あるいは10万円のいずれか高い金額から、着手金3万円を引いた金額 |
| 1,000万円~5,000万円 | 30,000円 | 調達金額のうち1,000万円を超える部分の1.5%に25万円を加えた金額から、着手金3万円を引いた金額 |
| 5,000万円超 | 30,000円 | 要御見積 |
| 調達金額 | 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 50,000円 | 調達金額の3%あるいは15万円のいずれか高い金額から、着手金5万円を引いた金額 |
| 1,000万円~5,000万円 | 50,000円 | 調達金額のうち1,000万円を超える部分の2%に30万円を加えた金額から、着手金5万円を引いた金額 |
| 5,000万円超 | 30,000円 | 要御見積 |
※ ただし資金調達支援後、顧問契約等継続的にお付き合い頂くことが前提の場合、顧問先のお客さまと同水準の報酬でお受けする場合もございます。
(融資コンサルティング業務)
(1)借入先金融機関の選定に関する助言、借入先金融機関の紹介
(2)融資申請書類の作成に関する助言及び補助
(3)創業計画・事業計画に基づく予測損益計算書、予測貸借対照表、資金繰り計画の作成
(4)金融機関との面談および実施調査に関する助言
(5)資金調達完了後のフォローアップ
(6)その他上記に付随する業務
Office
事務所名
会計事務所タクシス(伊藤篤史税理士事務所)
所在地
〒101-0043 東京都千代田区神田富山町7-708号
代表税理士
伊藤篤史・いとうあつし
Contact
お問い合わせフォームまたはお電話にてお問い合わせください。